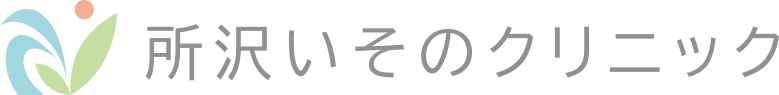Symptom
症状(内科)
症状(内科)
血糖値、HbA1cが高いと言われた
糖尿病とは
糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高くなってしまう病気です。私たちの身体は、食事で摂取した栄養素の一部をブドウ糖として血液中に運び、エネルギー源として活用しています。このブドウ糖を細胞へ取り込む際に重要な役割を果たしているのが、「インスリン」というホルモンです。
しかし、インスリンの量が不足したり、インスリンの働きが低下したりすると、血糖がうまく細胞内に取り込まれず、血液中のブドウ糖が過剰になる(高血糖状態)ことで様々な合併症を引き起こすリスクが高まります。糖尿病は初期段階ではほとんど自覚症状がないため、健康診断などで血糖値の異常を指摘された際には早めに受診することが大切です。
糖尿病の種類
糖尿病は大きく分けて1型糖尿病と2型糖尿病の2種類があります。日本人の多くは2型糖尿病が中心ですが、それぞれの特徴を理解しておくと治療や予防に役立ちます。
1. 1型糖尿病
1型糖尿病は、自己免疫などの原因によって**膵臓(すいぞう)**がインスリンを分泌できなくなるタイプです。子供から大人まで幅広い年代で発症し、突然血糖値が急上昇することがあります。インスリン分泌が極端に少ないため、インスリン注射による治療が不可欠です。
2. 2型糖尿病
2型糖尿病は、生活習慣の乱れや遺伝的要因などによってインスリンの働きが低下したり、分泌量が相対的に不足したりすることで発症します。日本人の糖尿病患者のおよそ95%が2型とされ、長い間自覚症状がほとんどないまま進行しがちです。放置すると、高血糖による血管障害により複数の合併症を引き起こす恐れがあるため、早期の発見と治療が重要になります。
糖尿病で起こる主な合併症
血糖値が高い状態が続くと、体内を巡る血管、とくに細い血管や末梢神経が徐々にダメージを受け、様々な合併症が起こるリスクが高まります。なかでも代表的なのが「3大合併症」と呼ばれる次の症状です。
1. 糖尿病神経障害
指先や足先などの末梢神経に障害が及ぶことで、しびれや感覚の異常、痛みに気づきにくくなるといった症状が表れます。さらに進行すると筋力の低下や立ちくらみ、発汗異常など自律神経にも悪影響を及ぼすことがあります。比較的早期から現れることが多いため、普段から手足のしびれや違和感に注意することがポイントです。
2. 糖尿病網膜症
眼球の奥にある網膜には視神経や毛細血管が密集しています。血管の障害が進むと、眼底出血や網膜のむくみを起こし、視野が狭くなる、視力が低下するなどのトラブルに見舞われます。重症化すると失明につながることもあり、日本では失明の原因として上位に挙げられます。初期にはほとんど自覚症状がないため、定期的な眼科検診(眼底検査など)で早期発見を心がけましょう。
3. 糖尿病腎症
腎臓は血液をろ過して老廃物を尿として排泄する大切な役割を担っています。糖尿病により血管が硬くなり(動脈硬化)、腎臓の微小血管がダメージを受けると、タンパク尿が出現したり、最終的には腎不全(人工透析が必要になる状態)に進行するリスクが高まります。日本の透析導入原因としてもっとも多いのが糖尿病腎症とされています。
その他の合併症
高血糖が続くことで動脈硬化が進行し、脳梗塞や心筋梗塞、下肢閉塞性動脈硬化症など重篤な病気を引き起こすリスクが高くなる場合があります。また、皮膚トラブルや感染症にかかりやすくなることも報告されています。定期的な検査や日々のケアで早期に異常を発見し、合併症の進行を防ぐことが非常に重要です。
糖尿病の検査と診断
糖尿病かどうかを調べるには、一般的に次のような検査を行います。
-
血液検査(血糖値・HbA1c)
血糖値が高いかどうかだけでなく、過去1~2か月間の血糖コントロールの状態を示すHbA1cの値も重要です。 -
尿検査(尿糖・尿タンパク)
尿に糖が出ているかどうか、腎機能に問題が起きていないかをチェックします。 -
眼科検診(眼底検査)
網膜症の早期発見に欠かせません。自覚症状がないうちに進行している場合もあります。
必要に応じて心電図、エコー検査、血管年齢測定などを行い、全身の血管状態や合併症の有無を総合的に判断します。これらの検査結果から、医師が診断を下し、患者さん一人ひとりに合った治療方針を提案します。
糖尿病の主な治療法
糖尿病の治療は、大きく分けて食事療法、運動療法、薬物療法の3つを柱としています。さらに患者さんの年齢、症状、生活スタイルなどに合わせて、医師や管理栄養士、看護師など多職種の医療チームがサポートを行います。
1. 食事療法
糖尿病治療の基本となるのが食事療法です。カロリー制限だけでなく、栄養バランスや摂取タイミングも重要になります。具体的には次のようなポイントを意識します。
-
適切なエネルギー量の設定(過剰摂取や極端な制限に注意)
-
バランスのよい栄養素の組み合わせ(タンパク質、脂質、炭水化物など)
-
食物繊維の積極的な摂取(野菜、海藻、きのこ類など)
医師や管理栄養士と相談しながら、無理なく続けられる食事内容を考えましょう。特に2型糖尿病の患者さんの場合、食事改善によって血糖コントロールが格段に良くなるケースも少なくありません。
2. 運動療法
適度な運動は、血糖値を下げるだけでなく、血液の循環を促進し、心肺機能や筋肉量を維持するうえでも大切です。ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなど、日常生活に無理なく取り入れやすい運動が推奨されます。個人差がありますが、週に3~5回程度、1回30分程度の有酸素運動を継続することが理想的といわれています。
ただし、心臓や関節に不安がある方は、主治医に相談のうえで運動強度を調整しましょう。
3. 薬物療法
血糖コントロールが食事療法や運動療法だけでは十分に得られない場合、経口血糖降下薬やインスリン注射などの薬物治療が検討されます。2型糖尿病は人によって原因や症状の現れ方が大きく異なるため、薬の種類もさまざまです。
-
経口薬: インスリンの分泌を促進する薬や、インスリン抵抗性を改善する薬、糖の吸収を抑える薬など
-
注射薬: インスリン製剤やGLP-1受容体作動薬など
特に2型糖尿病でも、病状が進むとインスリン注射が必要になるケースがあります。主治医とよく相談し、自分に合った薬物治療を継続することが合併症の予防・進行抑制につながります。
糖尿病療養指導の重要性
糖尿病は、日々の生活習慣が大きく影響する病気です。定期的な通院に加え、看護師や管理栄養士による療養指導を受けることで、より効果的に血糖コントロールを維持しやすくなります。具体的には以下のようなサポートを得られます。
-
血糖自己測定のアドバイス: 正しい測定のタイミングや測定機器の使い方、数値の見方を指導
-
インスリン注射の方法や注意点: 注射部位や針の取り扱い、低血糖時の対処など
-
日常生活での注意点: 食事や運動、睡眠のリズム、ストレスマネジメントなど
-
合併症予防のための定期的な検査項目: 眼底検査や尿検査、血液検査などの重要性について
こうした指導を受けることで、患者さん自身が日々のコントロールを主体的に行えるようになり、より安定した血糖管理が実現しやすくなります。
生活習慣改善のコツ
2型糖尿病は特に、長い年月をかけて生活習慣の乱れが蓄積し、血糖コントロールが乱れるケースが多くあります。以下のポイントを参考に、無理なく継続できる方法を見つけてみてください。
-
少しずつ取り組む
食事量を急に半分に減らしたり、激しい運動を毎日続けようとしても、長続きしにくいものです。最初は週に1回ウォーキングを増やす、炭水化物の量を少し控えるなど、できる範囲で徐々に習慣化することが大切です。 -
目標設定を具体的に
例:「1日5000歩以上歩く」「毎食野菜を先に食べる」など、数値や行動に落とし込むと継続しやすくなります。 -
モチベーションの維持
家族や友人と成果を共有する、定期的に通院して医師や管理栄養士にフィードバックをもらうなど、周囲のサポートを活用しましょう。 -
ストレス管理
ストレスは過食や不摂生を招きやすく、血糖値の乱れにもつながります。十分な睡眠と適度なリフレッシュ方法を取り入れて、心身のバランスを整えましょう。
当院ではプライバシーの配慮を徹底しており、全ての患者様を番号でお呼びしております。
ご予約はこちらからも承ります。
文責:院長 磯野誠
所沢いそのクリニック 内科・泌尿器科・女性泌尿器科
埼玉県所沢市東所沢2-24-8
04-2951-2200
※当院は、所沢市内および近隣の市町村(ふじみ野市、富士見市、三芳町、新座市、朝霞市、和光市、狭山市、入間市、日高市、飯能市、東京都清瀬市、東京都東村山市、東京都小平市、東京都国分寺市)からの患者様にも多くご利用いただいております。