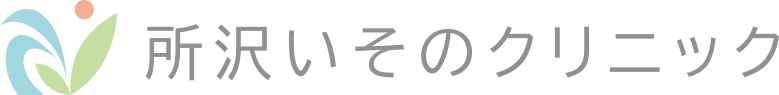Symptom
症状(泌尿器科)
症状(泌尿器科)
尿が出なくて苦しい(尿閉)
尿閉とは
尿閉は、大きく分けて「急性尿閉」と「慢性尿閉」に分類されます。急性尿閉は文字通り、ある日突然排尿ができなくなるタイプで、下腹部の強い痛みや尿意があるにもかかわらず排尿できない苦しさが特徴です。一方、慢性尿閉は少しずつ排尿困難が進行して残尿量が増え、膀胱に尿が溜まった状態で生活しているにもかかわらず強い尿意を感じにくくなるタイプです。
慢性の場合、最初は「尿のキレが悪い」「少し時間をかけないと排尿できない」などの軽い症状から始まり、残尿が増えるにしたがって「頻繁にトイレに行くが、すっきり出きらない」「お腹が張っているように感じる」といった状態に陥ります。そして進行すると、腎臓に負担をかけて腎機能が低下してしまう可能性もあるため注意が必要です。
尿閉の症状・特徴
・下腹部の痛みや張り感
尿閉が急性に起こると、膀胱に尿が充満して下腹部が痛んだり、圧迫されるような苦しさを感じたりします。膀胱が極度に膨らむと、触れるだけでも痛みを強く感じることが多いです。慢性の場合は急性ほどの強い痛みは少ないものの、「下腹部に常に圧迫感がある」「何となく張っている」という不快感が続きやすくなります。
・尿意があるのに排尿ができない
急性尿閉では突然排尿が不可能になるため、尿意があるのに出せない苦痛と不安感が非常に強くなります。冷や汗をかいたり、緊張のあまり心拍数や血圧が上昇することもあります。慢性の場合は、自覚しにくいほど少しずつ尿道や膀胱がダメージを受けるため、「きちんと排尿できている」と勘違いするケースがあります。実は毎回残尿が多く、本人が気づかないうちに尿閉状態へ移行していることもあるのです。
・少量ずつ尿が漏れる
慢性尿閉が進むと、膀胱内の圧力が高まり、少しずつ尿が漏れ出す「溢流性尿失禁」や「奇異性尿失禁」を引き起こすことがあります。下着が常に湿っていたり、尿特有のにおいを感じやすくなったりするため、こうしたサインも見逃さないようにしましょう。
・腰痛や発熱
尿閉にともない、尿が長く膀胱内にとどまった状態が続くと、膀胱から腎臓にまで影響を及ぼす恐れがあります。尿路感染症のリスクが高まる結果、腎盂腎炎(じんうじんえん)を併発し、腰の痛みや発熱などを引き起こす可能性があります。
急性尿閉と慢性尿閉
・急性尿閉
急にまったく排尿できなくなる状態です。強い尿意と下腹部痛があり、時には冷や汗や不安感、緊張なども伴います。多くの場合、膀胱そのものの収縮力はまだ保たれているといわれますが、前立腺肥大症を持つ男性が大量に飲酒したり、抗ヒスタミン薬入りの感冒薬や花粉症の薬を服用した後に起こりやすい傾向があります。また、手術後などにベッド上で排尿しようとしてうまくいかず、そのまま膀胱に尿が溜まって急性尿閉となるケースも見られます。
・慢性尿閉
長い時間をかけて排尿困難が進行し、残尿量が増え続けた状態です。初期には自覚症状が少なく、排尿回数が多くなっても「歳のせいかな」「疲れかな」などと見過ごされることがあります。しかし、徐々に膀胱が常に張っている状態になり、尿意を感じにくくなってしまうため、いつの間にか膀胱に大量の尿が溜まっているという事態に陥ります。この段階になると尿が漏れ始める場合もあり、「トイレに行く回数は多いのに、実際には残尿が多い」などの不安定な状態が続きます。放置すると腎臓への影響も懸念され、腎機能障害につながるリスクもあるため注意が必要です。
尿閉の主な原因
尿閉を引き起こす原因としては、大きく以下のようなものがあります。
-
下部尿路の通過障害
男性に多い前立腺肥大症が代表例です。前立腺が加齢などにより肥大化すると、尿道が圧迫されて排尿が困難になります。ほかにも尿道狭窄など、尿の通り道そのものに機械的な閉塞が生じると尿閉のリスクが高まります。 -
神経障害(神経因性膀胱)
脳や脊髄、末梢神経など、排尿をコントロールする神経系統に異常がある場合です。糖尿病にともなう末梢神経障害や、脊髄損傷などが挙げられます。神経が障害されると膀胱の収縮や尿意の伝達機能がうまく働かず、膀胱に尿が溜まっていても排出できない状態になります。 -
薬剤の影響
抗ヒスタミン薬、抗コリン薬(副交感神経遮断薬)、一部の降圧薬など、排尿筋の収縮を妨げたり、膀胱出口を締めつけたりする副作用を持つ薬剤があります。普段は問題にならなくても、複数の薬を併用することで相乗的に排尿困難を起こし、結果的に尿閉へつながることがあるので注意が必要です。 -
心理的要因
手術直後や慣れない環境での排尿を試みる際、緊張からうまく排尿できず、最終的に急性尿閉になってしまう例があります。入院中にベッド上排尿を試みて失敗したり、排尿時の姿勢が不自然だったりすると精神的に不安が高まりやすく、結果的に尿道や骨盤底筋が緊張して排尿を阻害してしまいます。 -
その他の誘因
気温の急激な低下や飲酒、性交など、瞬間的に交感神経が優位になったり、前立腺付近に炎症が起こったりすることで急激に尿閉が起こる場合があります。また、膀胱鏡検査などで膀胱や尿道に刺激を与えた後、痛みや不安から腹圧をかけにくくなることで尿閉に至ることもあります。
尿閉の検査・診断
尿閉が疑われる際には、以下のような検査が行われます。
-
問診・視診・触診
下腹部の膨らみや圧痛の有無を確認し、症状の経過を詳細に聞くことで急性か慢性かをある程度見極めます。 -
超音波検査(エコー)
膀胱にどのくらい尿が溜まっているかを確認できます。残尿量の測定にも用いられ、尿閉の有無や程度を把握する重要な手がかりとなります。 -
尿検査・血液検査
感染症の有無や腎機能の状態を確認し、他の合併症がないかを確認します。 -
画像検査(CT、MRIなど)
前立腺や尿道に腫瘍や結石がないか、神経に異常がないかなどを調べる場合があります。 -
膀胱鏡検査
必要に応じて、直接膀胱や尿道を観察して通過障害や炎症、病変部位を確認します。
尿閉の治療
・急性尿閉の緊急対応
急性尿閉の場合は、まずカテーテル(管)を挿入して膀胱内の尿を排出し、痛みや不快感を軽減させます。カテーテル留置により膀胱機能を休ませながら原因疾患を特定し、必要に応じて薬物療法を行います。例えば前立腺肥大症が原因であれば、α遮断薬など排尿を促進する薬を使用し、改善が見込めるかどうかを検討します。
・慢性尿閉の対処法
慢性尿閉では、残尿の程度や原因となる疾患・薬剤の有無を総合的に評価して、治療方針を決めます。前立腺肥大症の場合は薬物療法を試み、改善が乏しければ手術的治療を検討します。神経因性膀胱であれば、自己導尿(自分でカテーテルを挿入して排尿する方法)を指導し、膀胱内に尿が溜まりすぎないよう管理することがあります。
・薬剤調整
複数の薬を服用している場合、それらが排尿に悪影響を及ぼしていないかを医師や薬剤師が総合的に判断し、必要であれば服用薬を変更するなどの対処を行います。高齢の方では特に、抗コリン作用を持つ薬や抗ヒスタミン薬などが重なっているケースが多いため、こまめな服薬チェックが重要です。
・生活習慣の見直し
急な飲酒や寒冷刺激を避ける、適度な水分補給を行うなど、生活習慣を見直すことも尿閉のリスク軽減に役立ちます。特に前立腺肥大症を持つ方は、飲酒時や寒い環境下では尿閉が起こりやすいため、注意が必要です。
自己導尿(間欠自己導尿)とは
自己導尿とは、カテーテルと呼ばれる細い管を自分で尿道に挿入し、膀胱に溜まった尿を一定のタイミングで排出する方法です。医療用語では「CIC(Clean Intermittent Catheterization)」と呼ばれることもあります。排尿機能に問題がある方にとって、尿道にカテーテルを留置しっぱなしにする「留置カテーテル方式」に比べ、尿が必要以上に溜まらないよう定期的に排出することで、感染リスクの低減や生活の質向上につながりやすい点が特徴です。
※尿を排出するためにカテーテルを使う方法は、主に次の2種類に分かれます。
-
留置カテーテル(バルーンカテーテル)
文字通りカテーテルを常に尿道へ留置し、先端についている小さな風船(バルーン)を膀胱内で膨らませて固定するやり方です。一度挿入すればトイレに行く必要がなくなる反面、常にカテーテルと集尿袋を身につけなければいけないため、衛生管理や生活上の煩わしさが増します。体内に異物が留まっている状態が続くので、尿路感染のリスクが高まる点もデメリットです。 -
間欠自己導尿(CIC)
定められた時間おき、または尿意を感じたり必要性があるタイミングでカテーテルを挿入し、尿を排出し終わったらすぐに抜去する方法です。カテーテルを留置し続けないため、排尿以外の時間はカテーテルが体内になく、身体を動かしやすかったり、見た目の負担が少なかったりといった利点があります。また、残尿が多くならないよう管理しやすいので、膀胱や腎臓の負担を軽減する効果も期待できます。
自己導尿の回数と1回あたりの尿量
・1日の導尿回数
多くの場合、1日の導尿回数は3~6回程度が目安です。ただし、個人差や水分摂取量によって変わります。自力である程度の排尿が可能な方は1〜2回で済む場合もあれば、水分を多く摂る方は7〜8回必要になることもあります。回数が多いほど手間が増えますが、その分、膀胱に古い尿が長時間滞留せずに済むので、感染リスクの抑制につながりやすいというメリットがあります。
・1回の導尿量の目安
1度に排出される尿の量は、200~300ml程度が理想的とされています。500mlを超えるような状態が続くと、膀胱の粘膜が伸ばされて細菌が繁殖しやすくなるほか、膀胱炎のリスクが高まります。また、1日合計の排尿量(自己導尿+自然排尿)としては、1500ml前後が一般的な目標です。飲み物を取りすぎると膀胱に溜まる尿量が増え、導尿の回数も増えるため、適切な水分バランスを保つことが重要です。
自己導尿の具体的な手順
自己導尿は、基本的に以下のステップで行います。最初は慣れない動作が多いかもしれませんが、医師や看護師の指導を受けながら繰り返し練習することで、スムーズにできるようになります。
-
手洗い
石鹸と流水で両手をよく洗い、できるだけ清潔を保ちます。 -
尿道口の消毒
消毒綿やウェットシートで尿道の出口を拭き取り、雑菌が入りにくいようにします。 -
カテーテルの挿入
カテーテル先端に潤滑ゼリーをつける、あるいはもともとコーティングされたカテーテルを使用して、尿道にゆっくりと挿入します。-
男性の場合は15〜20cmほど挿入すると尿が出始めることが多いです。途中で引っかかるときは、陰茎をまっすぐに伸ばして角度を整えながら少し抜き挿しを試みると入りやすくなります。
-
女性の場合は4〜5cm程度で尿が出ることが多いですが、尿道口が視認しにくい場合は鏡を使って位置を確認するとスムーズです。
-
-
尿の排出を確認
尿が出始めたら、そのまま待ちます。いったん尿が止まっても、カテーテルを1cm刻みに引き抜くことで、膀胱の底に残った尿が再び出てくることがあります。 -
カテーテルの抜去
尿が完全に出なくなったと感じたら、カテーテルを抜きます。最後の数滴まで出し切ることで残尿量を減らし、感染リスクを下げることが可能です。 -
尿量の測定(必要に応じて)
導尿後の尿量を測定し、排尿日誌などに記録することで、適切な導尿回数や水分摂取量の調整を行いやすくなります。
導尿時のコツと注意点
-
清潔操作に神経質になりすぎない
手洗いや尿道口の消毒は大切ですが、完全に無菌にするのは難しいものです。むしろ重要なのは、尿を溜めすぎないことと最後までしっかり排出することです。 -
カテーテルを無理に押し込まない
途中で抵抗を感じたら、一旦少し抜いて角度を変えたり、陰茎や外陰部の向きを調整したりしてみましょう。何度も同じ場所で引っかかる場合や、出血・痛みが強い場合には主治医に相談してください。 -
排尿日誌の活用
①何時に自己導尿をしたか、②自然に出た尿の量、③導尿で出た尿の量を定期的に記録すると、導尿回数の最適化や、水分摂取の調整に役立ちます。受診の際にこれらのデータを持参すれば、医師がより適切なアドバイスを提供できます。 -
女性は鏡を活用して慣れる
尿道口の位置が分かりにくい場合、最初は鏡を使うのがオススメです。慣れてしまえば鏡がなくても行える方が大半です。 -
男性は陰茎をしっかり伸ばす
カーブがあるとカテーテルが途中で当たりやすいので、亀頭の下あたりを指で支えて陰茎をまっすぐにすると挿入しやすくなります。
使用するカテーテルの種類
自己導尿に使われるカテーテルには、大きく分けて2種類があります。
使い捨て型カテーテル(ディスポ)
個別包装されており、使用するたびに新しいものと交換します。「ネラトンカテーテル」と呼ばれる潤滑ゼリーを塗布して使うタイプや、あらかじめ液体に浸して潤滑コーティング済みの「浸水コーティングカテーテル」があります。前者は誰でも使用できますが、後者は一定の疾患(脊髄障害や二分脊椎など)に限定される場合があります。
再利用型カテーテル(セルフカテ)
消毒液と潤滑剤を入れた専用の容器にカテーテルを保管し、1本を約1ヶ月ほど繰り返し使うタイプです。使用後は容器に戻してフタを閉め、消毒潤滑液は1〜3日に一度交換します。
早期受診の重要性
「尿が出にくい」「残尿感がある」「トイレが近いわりにあまり出ない」「下着が知らないうちに湿っている」などの症状があれば、できるだけ早めに泌尿器科を受診しましょう。尿閉は放置すると腎機能障害や泌尿器感染症などを招き、全身に影響を及ぼす可能性があります。軽度の排尿困難のうちに対処できれば、薬物療法や生活習慣の改善だけで状態が大幅に改善することが少なくありません。
また、急性尿閉を一度起こした方は再発しやすい傾向もあります。再発防止のためには、原因となる疾患を治療・管理するだけでなく、飲酒や薬剤の影響など日常生活のリスク因子を取り除く工夫が重要です。
当院ではプライバシーの配慮を徹底しており、全ての患者様を番号でお呼びしております。
ご予約はこちらからも承ります。
文責:院長 磯野誠
所沢いそのクリニック 内科・泌尿器科・女性泌尿器科
埼玉県所沢市東所沢2-24-8
04-2951-2200
※当院は、所沢市内および近隣の市町村(富士見市、ふじみ野市、三芳町、新座市、朝霞市、和光市、狭山市、入間市、日高市、飯能市、東京都東村山市、東京都清瀬市、東京都小平市、東京都国分寺市)からの患者様にも多くご利用いただいております。