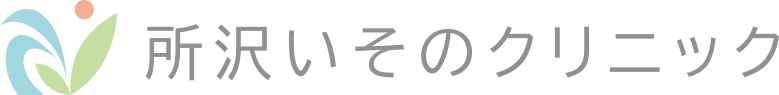Disease
病名(内科)
病名(内科)
脂質異常症、高コレステロール血症
脂質異常症とは?
脂質異常症(旧称:高脂血症)とは、血液中に含まれる脂質のバランスが崩れ、通常範囲を超えてしまった状態を指します。具体的には、中性脂肪(トリグリセライド)や善玉コレステロール(HDLコレステロール)、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)といった数値が、基準値から外れている状態を総称します。これらの数値は、動脈硬化の進行とも深く関わる重要な指標です。
中でもLDLコレステロールは血管内に蓄積しやすく、放っておくと動脈硬化が進行するリスクが高まります。一方、HDLコレステロールは余分なコレステロールを回収するはたらきを担っています。そのため、HDLコレステロールが不足すると、不要なコレステロールを十分に排出できず、動脈硬化のリスクが上がります。さらに、中性脂肪がきわめて高い状態では、LDLコレステロールを増加させ、HDLコレステロールを減らす方向に働く可能性があるため注意が必要です。
脂質異常症はどのように危険なのか?
脂質異常症は、それ自体で目立った自覚症状をもたらすことは多くありません。しかし、知らず知らずのうちに血管にコレステロールが蓄積され、動脈硬化が進行してしまう危険性があります。動脈硬化が進むと、下記のような疾患を引き起こすリスクが高まります。
- 脳血管疾患:脳梗塞や脳出血など
- 心疾患:心筋梗塞や狭心症など
- 腎臓病:血流障害により腎臓機能が低下
- 末梢血管障害:足の血管が詰まり、歩行障害やしびれを感じる場合もある
特に、糖尿病をお持ちの方や喫煙習慣がある方は、動脈硬化が複合的に悪化しやすいといわれています。脂質異常症はほかの生活習慣病と同時に進行することも少なくありませんので、定期的な検査と早期の対策がとても重要です。
脂質異常症の症状が分かりにくい理由
一般的に、脂質異常症は数値の異常があっても顕著な症状を感じない場合がほとんどです。健康診断で「コレステロールや中性脂肪が高い」と初めて指摘を受けて、脂質異常症であることを知る方が多くいらっしゃいます。中性脂肪とLDLコレステロールの上昇、あるいはHDLコレステロールの低下が長期化すると、血管のダメージが進行してしまうため、症状が出たときにはすでに動脈硬化が大きく進んでいることも珍しくありません。
また、中性脂肪が非常に高い状態では、膵炎を引き起こすリスクや血液が粘りやすくなる可能性があります。膵炎は激しい腹痛や吐き気をもたらす急性症状につながることもあるため、軽視できない問題です。数値は高いけれど体調に問題がないからと安心してしまうと、将来的に深刻な疾患に陥るリスクが高まります。
脂質異常症の原因とリスク要因
-
生活習慣の乱れ
脂質異常症を引き起こす最大の要因は、やはり生活習慣の乱れです。具体的には以下のような習慣が挙げられます。
暴飲暴食:高カロリー食・脂肪分の多い食事の過剰摂取
運動不足:消費カロリーより摂取カロリーが多い状態が継続する
不規則な食習慣:夜遅い時間の食事や間食の増加など
喫煙:善玉コレステロール(HDLコレステロール)の減少を促す
過度の飲酒:中性脂肪を上げる原因になりやすい
これらの要素が重なれば重なるほど、血液中の脂質バランスが崩れてしまう恐れが高まります。 -
遺伝的要因や痩せ型の方
まれなケースとして、遺伝的な理由によりコレステロールや中性脂肪が高くなる例もあります。特に、子どもの時から数値が高い場合や、痩せ型なのにLDLコレステロールが異常値を示す場合は、遺伝性の可能性を考え、専門医による検査が求められます。また、一見すると痩せていても、内臓脂肪が多い「かくれ肥満」の場合は、脂質異常症や糖尿病などの生活習慣病を発症しやすいため注意が必要です。 -
糖尿病や高血圧との相互影響
糖尿病や高血圧など、ほかの生活習慣病が既にある状態だと、脂質異常症を併発するリスクも高くなります。これらの疾患はそれぞれが独立しているわけではなく、相互に悪影響を及ぼすことが多いです。たとえば、糖尿病による高血糖状態は血管の内皮細胞を傷つけるため、動脈硬化が進みやすくなり、LDLコレステロールの蓄積を助長します。
脂質異常症の診断基準
通常、空腹時採血の結果に基づいて、脂質異常症かどうかを判定します。大まかなスクリーニングとして、以下の数値が目安となります。
- 中性脂肪(TG):150mg/dL以上
- HDLコレステロール:40mg/dL未満
- LDLコレステロール:140mg/dL以上(120〜139mg/dLの場合は境界域とされる)
ただし、これはあくまで一般的な基準であり、性別、年齢、喫煙の有無、家族歴、CKD(慢性腎臓病)、糖尿病などの合併症の有無など、個々のリスク要因に応じて目標値が変わります。もし健康診断で脂質の値を指摘された場合は、医師と相談して、ご自身に適した管理目標を確認することが大切です。
脂質異常症の予防・改善方法
-
食生活の見直し
脂質異常症の改善において、まず重要なのが食事療法です。食事量と質の両方に注意しながら、適正体重を維持することが目標になります。以下に注目した食事内容のポイントをまとめます。
(1) コレステロール摂取の制限
コレステロールは肝臓で合成されるものと、食事から摂取するものがあります。食事由来のコレステロールが過剰になると血中コレステロールが高まりやすいため、1日あたりの摂取量は200mgを超えないように心がけましょう。特に内臓類や卵類にはコレステロールが多く含まれているため、摂取頻度と量を意識することが大切です。
(2) 脂質の種類とバランス
脂質は大きく3種類に分類できます。
飽和脂肪酸(S):主に肉の脂身やバター、乳製品などに多く含まれ、コレステロールを上昇させやすい
多価不飽和脂肪酸(P):青魚や植物油に含まれ、コレステロール低下作用に寄与する
一価不飽和脂肪酸(M):オリーブオイルやアボカドに多く、LDLコレステロールを下げる効果も期待できる
飽和脂肪酸に偏らないように、魚や植物性の油を活用し、動物性脂肪を取りすぎないようにしましょう。また、マーガリンやショートニングに含まれるトランス脂肪酸は動脈硬化を進めるリスクがあるため、摂りすぎには要注意です。
(3) 食物繊維の積極的摂取
食物繊維は余分なコレステロールや糖分の吸収を抑える効果があり、脂質異常症の改善に役立ちます。野菜、海藻、きのこ類、豆類など、食物繊維を多く含む食品を毎食バランスよく取り入れましょう。特に、中性脂肪は糖分の過剰摂取でも上昇しますので、菓子や甘いジュースの飲み過ぎに気をつけてください。
(4) 糖質制限の活用
世界的に推奨されているアプローチの一つに糖質制限があります。カロリー全体を抑えるのではなく、糖質そのものを減らすため、お腹が空きにくいというメリットがあるのが特徴です。具体的には、ジュースやビール、菓子パンなど糖質の多い食品を減らし、代わりにタンパク質や野菜を増やす食事スタイルが勧められます。間食はナッツ、チーズ、豆乳など糖質の少ないものを選ぶとよいでしょう。
(5) 飲酒は適量にとどめる
アルコールには中性脂肪を増やすはたらきがあるため、過度の飲酒は控えましょう。また、アルコールはカロリーが高く、食事制限の意識を薄れさせやすい面もあります。飲む場合は少量にとどめ、おつまみも食物繊維や良質なタンパク質を含むメニューを選ぶなど、全体的にバランスを意識してください。
-
運動療法の取り入れ
心疾患やその他の持病をお持ちの場合は、必ず医師と相談のうえ、負担の少ない運動から始めましょう。日常に取り入れやすい方法としては、早歩きでのウォーキング(1日10分からでもOK)や、椅子から立ち上がるだけの簡単な椅子スクワットなど、無理なく継続できる種目がおすすめです。
食事改善とあわせて運動療法を行うと、より効果的に脂質異常症の改善が期待できます。運動により消費エネルギーが増えるため、体重管理がしやすくなり、中性脂肪の減少やHDLコレステロールの増加につながりやすいとされています。さらに、運動を続けることで血管が強くなり、血圧や血糖値の改善にもメリットがあるといわれています。 - 薬物療法
主に使用される薬には以下の種類があります。
スタチン系製剤(HMG-CoA還元酵素阻害剤)- コレステロール合成を抑制し、LDLコレステロールを大幅に低下させる
- 腸管でコレステロールの再吸収を抑える
- コレステロールの吸収そのものを阻害する
- LDLコレステロールと中性脂肪の両方を下げる効果がある
- 中性脂肪を下げる力が強く、HDLコレステロールを増やす場合も
- 青魚などに含まれる成分で、中性脂肪を低下させる効果が期待できる
薬の選択は、患者様の合併症の有無や重症度、目標値などを総合的に判断して行われます。いずれの場合も、服用を始めたら自己判断で中断せず、定期的な血液検査で効果と副作用を確認しながら継続することが大切です。
まとめ
脂質異常症は自覚症状が乏しいまま静かに進行し、動脈硬化をはじめとする重大な疾患のリスクを高める恐れがあります。健康診断や人間ドックで一度でもコレステロールや中性脂肪の異常を指摘されたことがある場合は、早めに医師に相談し、必要に応じて生活習慣の改善や薬物療法を検討しましょう。
- **生活習慣の見直し(食事・運動・禁煙・適量飲酒)**が基盤
- 数値に応じて適切な薬物療法を検討
- 合併症予防や治療のためには定期的な受診が不可欠
当院では、スタッフがチームでサポートし、患者様に合わせた最適な治療プランをご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。脂質異常症に対する理解を深め、日々の生活を見直すことが、将来の健康を守る大きな一歩となります。
ご予約はこちらからも承ります。
文責:院長 磯野誠
所沢いそのクリニック 内科・泌尿器科・女性泌尿器科
埼玉県所沢市東所沢2-24-8
04-2951-2200
※当院は、所沢市内および近隣の市町村(新座市、朝霞市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、和光市、狭山市、入間市、日高市、飯能市、東京都清瀬市、東京都東村山市、東京都小平市、東京都国分寺市)からの患者様にも多くご利用いただいております。