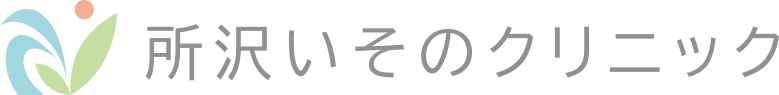Symptom
症状(泌尿器科)
症状(泌尿器科)
健康診断で尿潜血を指摘された
尿潜血とは
尿潜血(にょうせんけつ)とは、ぱっと見ただけではわからない程度の血液が尿中に混じっている状態を指します。一般的な健康診断での尿検査では「潜血反応」として検出されることが多く、医療機関を受診して初めて「尿に血が混じっている」と指摘されるケースが少なくありません。尿潜血が検出されたからといって、すぐに大きな病気があるとは限りませんが、原因を特定して必要な対処を行うためにも精密検査が重要です。
尿潜血の原因
尿潜血を起こす原因は大きく分けて以下のようなものが考えられます。
1. 膀胱・尿管など泌尿器に由来する病気
-
結石(腎臓結石・尿管結石・膀胱結石)
-
膀胱炎や尿道炎などの感染症
-
膀胱がんなどの悪性腫瘍
2. 腎臓に由来する病気
-
IgA腎症などの免疫異常による疾患
-
アルポート症候群などの遺伝性の疾患
-
慢性腎炎や急性腎炎など腎臓自体の炎症
3. その他
-
激しい運動直後に起こるミオグロビン尿
-
一部の薬剤による副作用
-
前立腺炎など前立腺のトラブル
これらの原因のうち、最も注意が必要なのは悪性腫瘍や進行性の腎臓病ですが、その他の比較的軽い要因でも尿潜血が出ることがあります。大切なのは、単に「潜血があるから危ない」と早合点せず、適切な検査で原因を突き止めることです。
尿潜血は「血尿」とどう違う?
「血尿」という言葉は、実際に尿が赤く見える状態を指すことが多いです。一方で、「尿潜血」は見た目にはほとんど変化がなく、尿検査の試験紙や顕微鏡検査で赤血球の存在が確認されるものです。いずれも尿に血液が混じっている点では同じですが、「血尿」は自覚しやすく、「尿潜血」は自覚症状がほとんどないという違いがあります。そのため、健康診断で潜血の指摘を受けて初めて発覚するケースが多く見られます。
健康診断でよく見る「尿潜血の数値」
健康診断の結果などでは、尿潜血はおおむね「(−)」「(±)」「(1+)」「(2+)」「(3+)」といった形で表示されます。
-
(−):陰性
全く潜血が検出されない状態です。 -
(±)〜(1+):軽度陽性
尿中に赤血球がわずかに混じっている可能性がありますが、偽陽性の場合もあり、日常生活での誤差の範囲に留まることも少なくありません。 -
(2+)〜(3+):明確な陽性
尿に比較的はっきりとした血液の混入が認められ、膀胱や腎臓に何らかの疾患が存在するリスクが高まります。
特に(2+)や(3+)と判定された場合には、尿沈渣(にょうちんさ)と呼ばれる顕微鏡での詳しい検査が推奨されます。同時に、血液検査や画像検査を含めた精査が必要となることが多いです。
尿潜血と他の指標がともに陽性の場合
-
尿潜血 + 細菌・白血球増加
膀胱炎や尿道炎などの感染症によって炎症が起こり、出血が伴っている場合があります。抗生剤などの薬物療法が必要かどうかを判断するため、泌尿器科の診察を受けるのが望ましいでしょう。
尿潜血 + 尿蛋白
尿潜血だけでなくタンパク(尿蛋白)まで陽性の場合は、腎臓のフィルター機能に何らかの障害がある可能性があります。IgA腎症をはじめとする糸球体疾患(腎炎など)のリスクが考えられるため、腎臓内科で詳しい検査を受けることが推奨されます。
詳しく調べるための検査方法
 尿潜血を指摘された際に医療機関で行われる主な検査は以下のとおりです。
尿潜血を指摘された際に医療機関で行われる主な検査は以下のとおりです。
1. 顕微鏡での精密検査(尿沈渣)
通常の健康診断で用いられる「試験紙法」は簡易的で、精度がやや低い場合もあります。そのため、潜血が見つかった場合には顕微鏡で実際に赤血球の有無や数、形状を調べる「尿沈渣」が行われます。赤血球の形によって、腎臓から出血しているのか、尿管や膀胱から出血しているのかをある程度推定できます。
2. 尿細胞診
膀胱がんなどの悪性細胞が尿中に含まれていないかを調べる検査です。年齢や喫煙歴、その他の症状などを考慮して必要性が判断されます。
3. 画像検査(腹部エコー・CTなど)
・腹部エコー(超音波検査): 体に負担が少なく、被ばくのリスクもない安全な検査です。腎臓や膀胱などの形態異常や結石の有無を評価できます。・CT検査: 尿管の結石や腫瘍など、超音波検査では把握しにくい病変をより詳しく画像化できます。必要に応じて医療機関から紹介状を発行し、設備の整った施設で受けるケースもあります。
4. 血液検査・培養検査など
腎臓の機能をチェックするための血液検査、尿中の細菌の種類を突き止めるための培養検査など、症状や疑われる病気に応じて追加の検査が行われます。
どの診療科を受診すればいいの?
尿潜血が見つかった場合、まずは泌尿器科の受診が一般的です。特に膀胱や尿管、尿道の病変が疑われるときには泌尿器科が専門となります。一方、尿蛋白も陽性で腎臓の異常が考えられる場合は、腎臓内科の受診も候補になります。
実際には「どちらを受診すればいいのかわからない」という方が多いですが、まずは泌尿器科もしくは腎臓内科のいずれかを受診し、必要に応じて別の科へ紹介してもらう流れでも問題ありません。医師に相談すれば、適切な診療科へ案内してもらえます。
診察・検査の流れの一例
-
初診での問診・尿検査
-
医師による問診(いつから症状があるのか、他に気になる症状はないかなど)
-
尿潜血の再検査、場合によっては血液検査を行う
-
-
再診・追加検査
-
腹部エコーや尿沈渣など、初診の結果を踏まえた追加の精密検査
-
病変の疑いがあればCTや尿細胞診を実施
-
-
結果説明・今後の治療方針決定
-
原因が特定できれば、薬物療法や生活指導などを開始
-
もし腎臓内科や別の診療科での治療が必要な場合、適切に紹介
-
尿潜血を放置しないために大切なこと
-
定期健診を受ける
健康診断を定期的に受けることで、症状がなくても早期に潜血を発見することができます。 -
自己判断せず医療機関を受診する
尿に血が混じる原因は多様です。生活習慣や一時的な運動などで検査値が変動することはあるものの、医師による診断なしに安心するのは危険です。 -
検査結果を見逃さない
尿潜血の異常が指摘された場合、「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、重症化した腎臓病や悪性腫瘍が見逃されるリスクがあります。少しでも不安を感じたら早めに再検査を受けましょう。
まとめ
尿潜血は自覚症状が乏しく、健康診断で初めて指摘される方が大半です。原因は多岐にわたり、腎臓の病気や泌尿器系の病気、あるいは一時的な運動や薬剤による影響など、軽度から重度までさまざまです。重要なのは、まずは専門の医療機関で精密検査を受けて自分の状態を正確に把握すること。そして、もし別の診療科が適している場合でも、医師に相談すれば速やかに連携施設を紹介してもらえます。
尿潜血は見た目にはわからないからこそ、早期発見と適切なケアが鍵を握ります。尿潜血の検査結果で不安を感じたら、放置せず医療機関へ相談することで、大きな病気を未然に防いだり、悪化を防ぐことができるでしょう。もしどの科を受診するか迷ったら、泌尿器科や腎臓内科に問い合わせてみてください。受診の入り口として相談すれば、最適な治療や検査の流れを提案してもらうことができます。
尿潜血について「もしかしたら放置しても大丈夫かも…」と考える方もいるかもしれませんが、身体のサインを見逃さないことが何よりも大切です。原因をはっきりさせて、必要なら早期に治療を始めることで、将来的なリスクを大きく減らせます。少しでも気になる症状がある方や、健診で尿潜血を指摘された方は、ぜひ医療機関へ気軽にご相談ください。
ご予約はこちらからも承ります。
文責:院長 磯野誠
所沢いそのクリニック 内科・泌尿器科・女性泌尿器科
埼玉県所沢市東所沢2-24-8
04-2951-2200
※当院は、所沢市内および近隣の市町村(ふじみ野市、富士見市、三芳町、新座市、朝霞市、和光市、狭山市、入間市、日高市、飯能市、東京都清瀬市、東京都東村山市、東京都小平市、東京都国分寺市)からの患者様にも多くご利用いただいております。